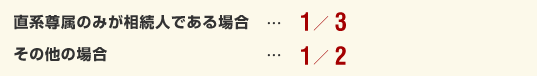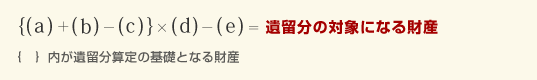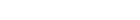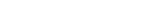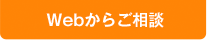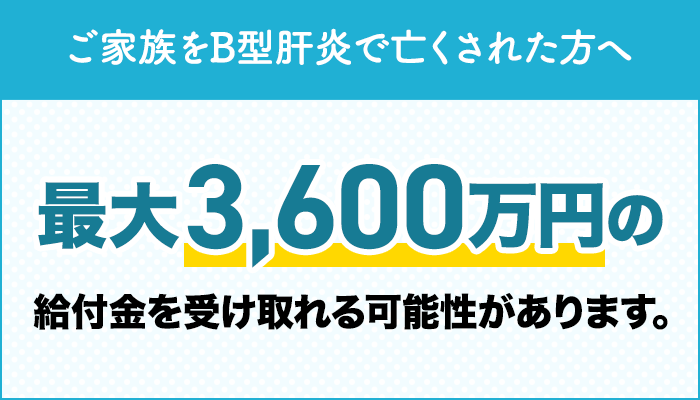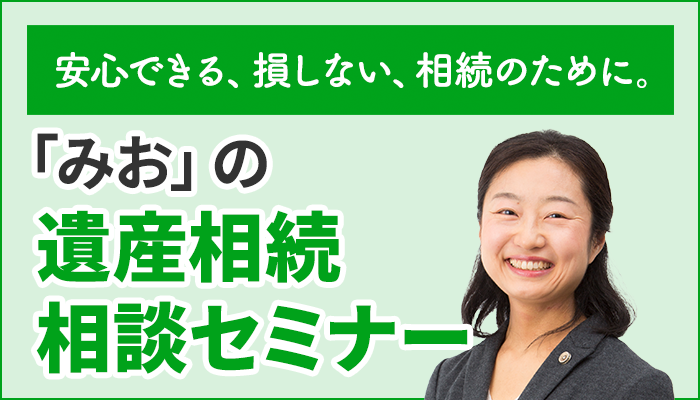1 遺留分権利者(遺留分を請求できる人)の確定
<配偶者><子(胎児も)><子の代襲相続人><直系尊属(父母・祖父母)>が権利者です。
亡くなった方の除籍謄本と相続人の戸籍謄本をとります。
- 配偶者・子
- 兄弟姉妹を除く法定相続人。養子も。
- 胎児
- 生まれると、子として遺留分が認められます。
- 代襲相続人
- 子供が亡くなっている場合にその子(亡くなった方の孫、場合によってはひ孫)
- 直系尊属
- 父母が亡くなっている場合には、祖父母
兄弟姉妹や、相続欠格・相続放棄・相続廃除者は請求できません。
2 遺留分の割合の確認
1 の結果をもとに遺留分の割合の計算をします。
遺留分の割合には、総体的遺留分と個別的遺留分があります。
- 総体的遺留分
- 遺留分権利者が相続財産全体に対して有する、遺留分の割合。
たとえば、相続人が
妻のみの場合・・・・1/2
子のみの場合・・・・1/2
配偶者と子の場合・・1/2
母のみの場合・・・・1/3
となります。
- 個別的遺留分
- 遺留分権利者が2人以上いる場合の、各人が有する遺留分の割合。総体的遺留分が法定相続分に従って分配されます。
たとえば、相続人が妻と子2人の場合の個別的遺留分は
妻・・・1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
子・・・1/2(総体的遺留分)×1/2×1/2(法定相続分)=1/8
となります。
3 遺留分の対象になる財産の調査・遺留分侵害額の確定
遺留分侵害額は、遺留分算定の基礎になる財産(a)〜(c)を調査し、原則として、下記の式で計算します。
-
(a) 亡くなった時の財産
不動産、預貯金、株式、動産、保険等を調査し、評価します。
-
(b) 贈与した財産
- ・遺贈
- 相続開始時に有していた財産に含まれます。
- ・死因贈与
- 死因贈与は遺贈と同じく取り扱うべきというのが多数説です。
- ・生前贈与
- 相続開始前の1年間にした贈与、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与であれば、相続開始の時に有していた財産に含まれます。また、相続開始前の10年間に相続人が婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与も、相続開始の時に有していた財産に含まれます。
-
(c) 債務額
債務には、私法上の債務のほか、公法上の債務(公租公課、罰金等)も含まれます。
なお、相続財産の負担となるべき費用、例えば相続財産に関する費用(相続税、相続財産管理費用等)、遺言執行に関する費用(検認申請費用等)は、控除すべき債務に含まれないとされています。
-
(d) 遺留分権利者の遺留分割合
-
(e) 遺留分権利者が既に受けている特別受益財産
-
(f) 遺留分権利者が相続によって得た財産の額
-
(g) 遺留分権利者が承継した債務の額